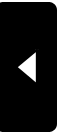2013年10月01日
香嵐渓シンポジウム2013
今年の香嵐渓シンポジウムの様子です。
総合司会の足助病院長早川富博氏が、講演演者として最初に紹介したのは、この方でした。
総合司会の足助病院長早川富博氏が、講演演者として最初に紹介したのは、この方でした。
北設楽郡設楽町津具地区の医療に7年半携わられたのち、現在は北海道の夕張市立診療所所長を務められている高木健太郎氏。
どちらの地域も高齢化率は45%とのこと。医療と介護と地域の連携について、両現場でのご経験を熱く語って下さいました。
どちらの地域も高齢化率は45%とのこと。医療と介護と地域の連携について、両現場でのご経験を熱く語って下さいました。
続いて、豊田市市民福祉部部長の今井弘明氏。
保健・医療・福祉に関する行政策と中山間地域の実情についてご報告いただきました。
地域包括ケアシステムの中心となる地域包括支援センターと地域ケア会議、地域見守り会議の紹介に加えて、里山健康学び舎事業、里山げんきグループ活動支援事業、地域ふれあい通所事業といった保健事業について解説いただきました。
画一化したシステムではなく、各地域の特性にあったシステムを作り上げることが必要であると語られました。
地域包括ケアシステムの中心となる地域包括支援センターと地域ケア会議、地域見守り会議の紹介に加えて、里山健康学び舎事業、里山げんきグループ活動支援事業、地域ふれあい通所事業といった保健事業について解説いただきました。
画一化したシステムではなく、各地域の特性にあったシステムを作り上げることが必要であると語られました。
はるばる島根県から足助までお越し下さったのは、島根大学疾病予知予防プロジェクトセンター専任講師の濱野強氏。
「健康を支える地域の力」と題して、2006年より開始された中山間地域を対象とする地域力(地域のつながり)研究プロジェクトについてご紹介下さいました。
無理の無い健康づくり活動を行うためには、地域性や地域に住む人々のつながりを知ることが大切である、とおっしゃる濱野氏が掲げられた「地域づくりは健康づくり」というキーワードに、多くの聴講者がうなづいてしました。
「健康を支える地域の力」と題して、2006年より開始された中山間地域を対象とする地域力(地域のつながり)研究プロジェクトについてご紹介下さいました。
無理の無い健康づくり活動を行うためには、地域性や地域に住む人々のつながりを知ることが大切である、とおっしゃる濱野氏が掲げられた「地域づくりは健康づくり」というキーワードに、多くの聴講者がうなづいてしました。
2013年09月30日
足助病院祭と香嵐渓シンポジウム #2
13時からは、南棟にある講義室にて、第4回香嵐渓シンポジウムが開催されました。
シンポジウムのテーマは、「健康は地域でつくる」 ~地域包括ケアネットワークを考える~ というもの。
総合司会は、足助病院院長の早川富博氏。
シンポジウムを主催した、三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会の会長も兼務されています。
なお、冒頭の挨拶で、昨年のシンポジウムの開催記録を綴った冊子をご紹介されました。来場者、関係者に配布されたこの冊子は、研究会事務局に若干の在庫があり、現在のところ希望すれば入手が可能です。
シンポジウムを主催した、三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会の会長も兼務されています。
なお、冒頭の挨拶で、昨年のシンポジウムの開催記録を綴った冊子をご紹介されました。来場者、関係者に配布されたこの冊子は、研究会事務局に若干の在庫があり、現在のところ希望すれば入手が可能です。
2013年の香嵐渓シンポジウムのゲストは、津具診療所所長として津具地区の医療に携わられたのち、現在は北海道の夕張市立診療所所長を務められている高木健太郎氏をはじめとして、豊田市市民福祉部部長の今井弘明氏、島根大学疾病予知予防プロジェクトセンター専任講師の濱野強氏の御三方でした。
To be continued.
To be continued.
2013年09月30日
足助病院祭と香嵐渓シンポジウム
前回の記事の続きです。
写真で当日の様子をご紹介します。
まずは病院祭の方から。









写真で当日の様子をご紹介します。
まずは病院祭の方から。









2013年09月28日
第4回香嵐渓シンポジウム 開催中
本日、足助病院南棟一階講義室にて、第4回香嵐渓シンポジウムが開催されています。
時間は15:20まで。
足助病院祭にお越しの方、お近くの方、お席は若干ありますのでいまからでもどうぞ。
シンポジウムの内容については会場の様子をおさめた写真を交えてまたあらためてこのブログにてご報告いたします。
時間は15:20まで。
足助病院祭にお越しの方、お近くの方、お席は若干ありますのでいまからでもどうぞ。
シンポジウムの内容については会場の様子をおさめた写真を交えてまたあらためてこのブログにてご報告いたします。

2013年09月20日
第4回 香嵐渓シンポジウム開催のお知らせ
◯とき
平成25年9月28日(土)午後1時より
◯場所
足助病院講義室
◯テーマ
「人がつくる地域包括ケア」
ートータルな健康(well being)ー
◯演者
希望の杜夕張市立診療所
所長 高木健太郎氏
豊田市役所市民福祉部
部長 今井弘明氏
島根大学疾病予知予防研究拠点
専任講師 濱野 強氏
*テーマ提案・総合司会
足助病院病院長(三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会会長)
早川 富博氏


今回のシンポジウムは、足助病院の病院祭と同日に、足助病院内にて開催されます。
ぜひ足をお運びください。
平成25年9月28日(土)午後1時より
◯場所
足助病院講義室
◯テーマ
「人がつくる地域包括ケア」
ートータルな健康(well being)ー
◯演者
希望の杜夕張市立診療所
所長 高木健太郎氏
豊田市役所市民福祉部
部長 今井弘明氏
島根大学疾病予知予防研究拠点
専任講師 濱野 強氏
*テーマ提案・総合司会
足助病院病院長(三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会会長)
早川 富博氏


今回のシンポジウムは、足助病院の病院祭と同日に、足助病院内にて開催されます。
ぜひ足をお運びください。
2013年09月19日
学習会のお知らせ
周りの人々に知られぬよう、相手の身体を傷つけることなく言葉や態度で心を繰り返し痛め続け、自尊心を破壊して物のように扱って支配しようとする卑劣ないじめ行為を、近年モラル・ハラスメントと呼ぶようになりました。
職場、学校、家庭。
日常に潜む、人の"心"に対する見えにくい暴力を、フランスの医師が緻密に分析・研究して概念化し、世界に向け発表したためです。
本年10月に、三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会が活動協力している団体である、ボランティアサークル 山里センチメンツが、熊本県のNPO "こころのサポートセンター・ウィズ" より専門家の方をお招きして講演会を開催します。
またその前に自主学習会を行います。
今回はその事前学習会のお知らせです。
お知り合いや職場の仲間を、ご友人を、ご家族を、そしてご自身を守るために、会場近隣にお住まいの方はぜひご参加ください。
記
日時:9月20日(金) 午後6:30〜
場所:愛知県豊田市小渡町船戸15-1 旭交流館
主催:山里センチメンツ
問合せ先:anti.moral.harassment.project@gmail.com
*本事業は、平成25年度豊田市わくわく事業の補助金交付対象として認められた事業の一環です。
*お住まいの地域に関係なく、モラル・ハラスメント問題に関心のある方ならどなたでも参加できます。
*学習会開始の15分前に開場します。
*講師/進行は、山里センチメンツのスタッフが務めます。
*所要時間は一時間から一時間半程度を予定しています。適度に休憩を挟みます。
*プロジェクターを用いてパワーポイントで作成した資料をお示しする形式で行います。
*簡単なレジュメは配布させていただきますが、必要に応じて筆記具、ノートなどを各自ご用意ください。
*プロジェクターを用いてパワーポイントで作成した資料をお示しする形式で行います。また簡単なレジュメは配布させていただきます。必要に応じ筆記具、ノートなどを各自ご用意ください。
*お茶、お水など、飲み物は各自ご用意ください。
*夕食の用意はいたしません。また会場内での食事はお控えください。
*他の参加者に迷惑をかける暴力的不良行為等を禁止します。
*運営スタッフはボランティアです。会場準備・片づけ作業など、ご協力いただけると助かります。
*10月20日(日)に熊本県のNPOより専門家の方を招き『モラル・ハラスメント被害をなくすための講演会』を開催します。詳しくは近くなりましたらお知らせいたします。

職場、学校、家庭。
日常に潜む、人の"心"に対する見えにくい暴力を、フランスの医師が緻密に分析・研究して概念化し、世界に向け発表したためです。
本年10月に、三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会が活動協力している団体である、ボランティアサークル 山里センチメンツが、熊本県のNPO "こころのサポートセンター・ウィズ" より専門家の方をお招きして講演会を開催します。
またその前に自主学習会を行います。
今回はその事前学習会のお知らせです。
お知り合いや職場の仲間を、ご友人を、ご家族を、そしてご自身を守るために、会場近隣にお住まいの方はぜひご参加ください。
記
日時:9月20日(金) 午後6:30〜
場所:愛知県豊田市小渡町船戸15-1 旭交流館
主催:山里センチメンツ
問合せ先:anti.moral.harassment.project@gmail.com
*本事業は、平成25年度豊田市わくわく事業の補助金交付対象として認められた事業の一環です。
*お住まいの地域に関係なく、モラル・ハラスメント問題に関心のある方ならどなたでも参加できます。
*学習会開始の15分前に開場します。
*講師/進行は、山里センチメンツのスタッフが務めます。
*所要時間は一時間から一時間半程度を予定しています。適度に休憩を挟みます。
*プロジェクターを用いてパワーポイントで作成した資料をお示しする形式で行います。
*簡単なレジュメは配布させていただきますが、必要に応じて筆記具、ノートなどを各自ご用意ください。
*プロジェクターを用いてパワーポイントで作成した資料をお示しする形式で行います。また簡単なレジュメは配布させていただきます。必要に応じ筆記具、ノートなどを各自ご用意ください。
*お茶、お水など、飲み物は各自ご用意ください。
*夕食の用意はいたしません。また会場内での食事はお控えください。
*他の参加者に迷惑をかける暴力的不良行為等を禁止します。
*運営スタッフはボランティアです。会場準備・片づけ作業など、ご協力いただけると助かります。
*10月20日(日)に熊本県のNPOより専門家の方を招き『モラル・ハラスメント被害をなくすための講演会』を開催します。詳しくは近くなりましたらお知らせいたします。

2013年08月20日
河合正嗣絵画展 開催中
河合正嗣さんの絵画展は、足助病院にて今月末まで開催しています。
ぜひ足をお運びください。
ぜひ足をお運びください。


2013年05月23日
三重大学に地域包括ケア・老年医学産学官連携講座が誕生
地域から育っている地域包括ケアが、大学でも本格的に研究され始めています。
昨年(2012年)10月、「地域包括ケア」の名を冠する講座として初めて、名古屋大学にて地域包括ケアシステム学寄附講座が設置され、次いで今年4月、三重大学に「地域包括ケア・老年医学産学官連携講座」が設立されました。
昨年(2012年)10月、「地域包括ケア」の名を冠する講座として初めて、名古屋大学にて地域包括ケアシステム学寄附講座が設置され、次いで今年4月、三重大学に「地域包括ケア・老年医学産学官連携講座」が設立されました。

先日、研究会に参加していただいた大西丈二先生 (写真の向かって左側の方) はこの三重大学の講座の准教授で、地域包括ケアを足助で学びたいと足を運ばれました。
地域は地域、病院は病院、大学は大学と、それぞれ役割を果たしながら、よい連携を持ち、安心して暮らし続けられる地域づくりを進めたいものです。
三重大学地域包括ケア・老年医学産学官連携講座
http://www.medic.mie-u.ac.jp/geriatrics/
主な情報はfacebook
https://www.facebook.com/mie.geriatrics だそうです。
(注:本記事は大西先生への取材を元に構成いたしました。)
2013年05月18日
足助村塾にて

昨日5月27日(金)、足助病院内にて恒例の足助村塾が開催されました。
足助村塾とは、医師や薬剤師、看護師、技士などの医療スタッフの皆さんが講師を務める講演会です。
地域に住まわれている一般の方々に向けた情報発信の場ですので、誰でも気軽に訪れて無料で医療・福祉等に関する話を聴くことができます。
上の写真は始まる前の会場の様子です。
この夜も、勉強熱心な聴講者の方たちが集まりました。
今回足助村塾を取り上げさせていただいたのは、この夜の講師が足助病院医療情報室顧問である杉浦正士氏で、話の内容が"いきいき生活支援事業の取り組み"についてだったからです。
杉浦氏は、三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワークの事務局業務も担当されており、さらに研究会が行っている『いきいき生活支援』という送迎・配食サービスにおける実際の運用のコントローラーをされています。
約一時間に渡り、二年間の実績紹介と事業効果の検証二結果についてわかりやすく解説してくださいました。

(写真中央の黄色いネクタイをつけ白いシャツを着た方が杉浦さん。後姿しか撮れませんでした、すみません。)
足助村塾とは、医師や薬剤師、看護師、技士などの医療スタッフの皆さんが講師を務める講演会です。
地域に住まわれている一般の方々に向けた情報発信の場ですので、誰でも気軽に訪れて無料で医療・福祉等に関する話を聴くことができます。
上の写真は始まる前の会場の様子です。
この夜も、勉強熱心な聴講者の方たちが集まりました。
今回足助村塾を取り上げさせていただいたのは、この夜の講師が足助病院医療情報室顧問である杉浦正士氏で、話の内容が"いきいき生活支援事業の取り組み"についてだったからです。
杉浦氏は、三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワークの事務局業務も担当されており、さらに研究会が行っている『いきいき生活支援』という送迎・配食サービスにおける実際の運用のコントローラーをされています。
約一時間に渡り、二年間の実績紹介と事業効果の検証二結果についてわかりやすく解説してくださいました。

(写真中央の黄色いネクタイをつけ白いシャツを着た方が杉浦さん。後姿しか撮れませんでした、すみません。)
2013年04月29日
第14回意見交換会
4月26日金曜日の19時より、足助病院内の会議室にて開催されました。

こちらは、初参加された大西先生と研究会会長である足助病院長早川先生のツーショットです。(大西先生のご経歴は次回の記事にてご紹介します。)
次第は下記の通りです。
1.病院のコミュニティ機能について考える (意見交換)
○いきいきサロンの開設について
・担い手、人材の育成
・財源問題
・その他
2.平成24年度総務省「ICT街づくり推進事業」 (報告)
豊田市『市民参加型ICTスマートタウン』への協力について
3.第4回 香嵐渓シンポジウムの開催に向けて (報告)
4.平成24年度「いきいき生活支援事業」について (報告)
☆配食サービス
進捗報告
☆送迎サービス
進捗報告
☆ロコモ予防教室
進捗報告
5.その他 意見・情報交換
またこの日は2013年度に取り組む事業と活動について、そのタイムスケジュールが示されました。
病院の新築・改修工事を終える6月以降は、病院をコミュニティの拠点とする構想をどんどん進めてゆくとのこと。
9月には第四4回となる香嵐渓シンポジウム、10月には研究会の総会が開かれます。
また、難病であるデュシェンヌ型筋ジストロフィーと闘うアーティスト、河合正嗣氏の絵画展2013を7月29日~8月31日に開催する予定であることが発表されました。



(交換会を終えて外に出たときに撮影しました。みなさん、遅くまで大変お疲れさまでした。)
2013年03月28日
2013年02月18日
事務局のご紹介

三河中山間地域で安心して暮らし続けるためのネットワーク研究会の事務局は、愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院内に設置されています。
向かって左から、後藤継一郎氏、杉浦正士氏、白井善男氏。
研究会発足時から会を支えていらっしゃった方々です。
研究会発足時から会を支えていらっしゃった方々です。

研究会への入会に関するご案内は近日中にこのブログにアップします。
少々お待ち下さい。
少々お待ち下さい。
2013年02月16日
第13回意見交換会


"三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会"という、とても長い名前の研究会の第13回意見交換会が開催されましたので、その様子をご紹介いたします。
これまでは、事務局が設置されている足助病院内の小ぶりな会議室で肩を寄せ合い行ってきましたが、今回はつい最近完成したばかりの同院新玄関前の広々としたホールに集いました。
これまでは、事務局が設置されている足助病院内の小ぶりな会議室で肩を寄せ合い行ってきましたが、今回はつい最近完成したばかりの同院新玄関前の広々としたホールに集いました。

「三河中山間地域で安心して暮らし続けるために」というとてもシンプルなキーワードを軸に様々な顔ぶれが隔月にて一堂に会し、関わるネットワーク構築を図ろうと模索するのがこの意見交換会の特色です。
今回は毎回出席されている一般住民の方々、足助病院関係者の方々に加え、地域医療を支えてくださっている各医院、診療所の先生方も多数参加され、いつもにまして盛況な意見交換会となりました。
次第は下記の通り。
1.平成24年度 総務省「ICT街づくり推進事業」豊田市『市民参加型ICTスマートタウン』について
2.第4回 香嵐渓シンポジウムの開催に向けて(意見交換)
3.平成24年度 「いきいき生活支援事業」について(報告:配食サービス、送迎サービス、ロコモ予防教室)
4.その他 意見・情報交換
意見交換がなされたこれらの取り組みは、ひとつの記事でまとめてポイと書けてしまうような内容ではないため、今後このブログ等にてぼちぼちご紹介してまいります。
お楽しみに。
今回は毎回出席されている一般住民の方々、足助病院関係者の方々に加え、地域医療を支えてくださっている各医院、診療所の先生方も多数参加され、いつもにまして盛況な意見交換会となりました。
次第は下記の通り。
1.平成24年度 総務省「ICT街づくり推進事業」豊田市『市民参加型ICTスマートタウン』について
2.第4回 香嵐渓シンポジウムの開催に向けて(意見交換)
3.平成24年度 「いきいき生活支援事業」について(報告:配食サービス、送迎サービス、ロコモ予防教室)
4.その他 意見・情報交換
意見交換がなされたこれらの取り組みは、ひとつの記事でまとめてポイと書けてしまうような内容ではないため、今後このブログ等にてぼちぼちご紹介してまいります。
お楽しみに。
2013年02月08日
【 香嵐渓シンポジウム 2011 】 開催記録
2012年の香嵐渓シンポジウムの会場にて、その前年となる2011年の開催記録を綴った冊子が配布されました。
研究会の会長である足助病院長の早川先生とともにNPO法人「共存の森」から澁澤寿一氏、足助商工会から浅井恒和氏、NPO法人 地域の未来・支援センターから萩原善之氏、くくのち学舎から渕上周平氏、農協共済総合研究所から川井真氏が登壇され、足助病院の後藤継一郎事務長が開会を宣言するとともに、シンポジウムの総合コーディーネーターとしてお招きした川井真氏を紹介されるところから記録は始まります。
どんな内容だったのか、以下に簡単にまとめましたので興味のある方はどうぞご覧ください。
研究会の会長である足助病院長の早川先生とともにNPO法人「共存の森」から澁澤寿一氏、足助商工会から浅井恒和氏、NPO法人 地域の未来・支援センターから萩原善之氏、くくのち学舎から渕上周平氏、農協共済総合研究所から川井真氏が登壇され、足助病院の後藤継一郎事務長が開会を宣言するとともに、シンポジウムの総合コーディーネーターとしてお招きした川井真氏を紹介されるところから記録は始まります。
どんな内容だったのか、以下に簡単にまとめましたので興味のある方はどうぞご覧ください。

農協共済総合研究所の川井氏が自己紹介の挨拶にて、
・日本中のあらゆる人々が様々な不安を抱えているが、質は違えど実は根本は極めて似通った問題で苦悩し続けている
・それらの問題を解決する手段のひとつとして地域力が求められている
・日本の後を追うように今後急速に高齢化の道を辿るアジアの他の国々は、一足早く正念場を迎えている日本がどう乗り切るかを注視しているのでうまく乗り切れば新しい社会モデルをアジアに示すことになる
・自然から搾取するのではなく自然と共に生きてきた日本人の強みと島国という日本の地理的強みなど地域力を高めやすい要素が揃っている
と話されました。
その後、川井氏が早川先生を紹介され、早川先生から「三河中山間の地域力を考える」~中山間地域における当院の取り組み~というタイトルで、スライドを用いながらの趣旨説明が始まり、病院と研究会の両方について様々な取り組みの詳細を語られています。
基調講演は「日本の里山に生きること」というタイトルにて澁澤寿一氏が
・日本は(2011年の)3月11日を境に変わった、高度成長の末に震災を経て全部を都会に集中させる社会から分散型社会に舵が切ろうとする人々が現れ始めた
・しかし実はそもそも日本は昔から地域の独立性で生きてきた国だった
・人任せの社会からもう一度自分たちでものを考える社会にすべきだと思う
・地球一個は足りなくなっている、つまりこのままでは70億人が地球一個で生きられなくなる時が訪れてしまう
という問題提起をされたのち、ご自身が秋田の山奥の集落をこの20数年間訪ね続けているというエピソードを紹介されます。その昔、秋田では過去に大規模な飢饉が起きて大勢の人々が命を落としているが、その集落では古文書が残っている過去300年間において一人の餓死者も出していないというのが通い出したきっかけだそうです。ここには書きませんが、その秘密はとても興味深いものでした。
他にも、山形の置賜地方の草木塔や馬頭観音、庚申塚、お不動さんの写真を紹介し、人々が自然といかに共生しようとしてきたかについて語られたり、沖縄のオジイ、オバアが生きる上で大切にしているポリシーのようなものの紹介など、その場でぜひ聴きたかったと思えるエピソードが続きます。
・生活はつくるものだということがもう一度見直される
・そして中山間地域での生き方がもう一度見直される時代がくると思っている
澁澤さんは聴衆に向かってそう語りかけています。
コーディネーターの農協共済総合研究所 川井氏に促され、足助病院長の早川富博先生と澁澤寿一氏が再び壇上に上がり、フロアーからの質疑応答の時間となりました。
地元の高校生からは
・少子高齢化となってきているのを自身も感じている
・もっと若い人たちが活発に暮すことができれば子供が増えていくのかなと思う
というような発言があり、それに対して早川先生からは
・ここ数十年に繰り広げられたような消費社会のままでいくのか、50年前の暮しに戻るのか、50年前と現代の中間みたいなところを目指すのか、若い世代の方が今後どのような生活を目指すのかがポイントになるのでは
とのコメントが。
澁澤氏は
・足助は底を打って上がり始めているのかもしれないと思う
・空家バンクに申込者が殺到したりしている状況があり、若夫婦が都会から何組かやってきている
・年にひと組ぐらいずつ入ってくるだけで数が確実に維持できるし、あるいは上がってくる
・都会からやってくる若者を各集落が温かく抱え込んでいただければ多分順調に足助は伸びてゆくと感じる
・年収700万、1000万を目指しましょうという時代ではないと思う。
と語られ、消費に重きが置かれたこれまでの生活に最早価値観を見いださず、心身ともに豊かに暮らすためにむしろ生活のサイズダウンすることを望む若者が増えているとおっしゃっています。
そして
・豊田の中山間地域は人が今まで出て行った比率がものすごく大きいからその人たちが帰ってくる余力は他のところに比べたら全然違う
・このあたりの若い人たちは旧豊田市内やせいぜい名古屋など、週に一回実家に帰ろうと思えば帰ることが出来る近距離に出ている人が多いため地域とのつながりが確実に残っている。
・都市と中山間地を組み合わせた生活、そういう生き方をチョイスしたいと若い人たちが思えばものすごくチョイスができる魅力的な地域だと思う
と続けられます。
コーディネーターの川井氏が澁澤氏の発言に「目からうろこでした。」と言われ、フロアーにいる聴衆が思い浮かべるイメージがさらに膨らむように
・ある程度の産業が整った町と、農林業を中心とした山間部での第一次産業とのコラボレーションがとりやすい地域なのかもしれない
と補足のコメントをされました。
そして、「ほかにどうですか。何か今のお話を聞いて。」と会場に呼びかけます。
すると、79歳の方がマイクを握って次のようなことを語り始めました。
・昔の生活はつらかった。親父と一緒に山に行き炭を焚き、雨が降っても田植えをする、それも手で。一日中這いつくばっていて腰が痛くてしょうがない。同時にお金もない。百姓と、山仕事と、貧乏が一番嫌いだった。
・その後、石油を利用するようになり、新幹線や車が走る時代になり、百姓をやるにも、移動をするにも文明の恩恵を受けてきたが、それはそれで昔のつらい暮らしぶりのことを思えば意義があると思える。
・決して間違いではなかったと思うが、地球環境の良くない変化だとか、身近なところでは山が荒れて、耕地も荒れてという様子になってきたのを見て、自然に寄りそう暮らしを望む人々が現れるのは、人間が長く生きる間のサイクルとして理解できる。
・早川先生は「会をつくってこれからみんなでやっていく、会員には息子や孫を入れていく」ということをおっしゃっていたが、「田舎に帰ってこいよ」という話があってもなかなか思うようにはいかない現実があるし、どういう風に手をつけて良いのかと思い悩んでいるこの足助が渋澤先生がおっしゃったように本当に良い方向に今後進んでいけるのか、ジリ貧ではないのか、と不安に思う。
・しかし弱気にならずに、力強く生きていかねばならない、とも思っている。
と正直な気持ちを語られました。
澁澤氏は
・まさにおっしゃったサイクルで、もう一回どこまで戻れるかを探していくことになり、それは地域ごとの個性になってくると思う
・お婆ちゃんたちに、どこまでだったら戻れるかと聞いたことがある。つらい暮らしを変えてくれた農業機械の話で例えて考えてもらったら、我々は便利さをとっくに通過してしまったことがわかった
・これからは確実に、便利になっていくのではなく、ある不便さを伴う形に世の中全体が、都市だ地方だということに関わらずなっていくが、それをどう喜びに変えられるかというのは、その地域の知恵だと思う
・あの時代に戻れとは思っていないが、行き過ぎてしまったことだけははっきりしている
・一体どこまで戻れるかということを皆さんと考えていくことが大事であり、その中のひとつが医療の問題なのかなと感じる
早川院長は
・ジリ貧ということで言えば、病院を立て直すときに人口推移のシミュレーションをしたところ、いまのままでいったとしても20年後までは大丈夫という試算 (病院経営が可能という試算) がなされた、しかし地域の人口は少しずつ減っていく
・外に出たご子息も定年退職されたら帰ってくればいい、帰ってきたところに楽しい地域を作っておく、じじばばが住むには医療と介護のセーフティネットが必要、セーフティネットにお金をかけすぎてはいけないのでお金をかけずにどういうセーフティネットをつくるのかというのがぼくらが考えること
・お金が入らない病院は消滅してしまうかもしれないが、そうではないという政策・方法をかんがえた場合は予防医学でいくことになる
・これからは、いかに生きるかということはいかに死ぬかということとイコールになる
・死に方にはいろいろあって良いはずで、家で、病院で、施設で、と最後の最後のところでは選択肢がいろいろあるという多様性を社会がある程度担保するのが理想
・健康的に生きる、あまり病まないように生きるための予防的な医療をしていきたい
・この地域で60代以上の方が楽しみをもって元気でいきいきと生きていることが大事、僕らはみなさんが安心していきいきとされるためのセーフティネットで下支えをするつもりである、そしてそれはできるのではないかと思っている
と、それぞれ心強いコメントを返されました。
・日本中のあらゆる人々が様々な不安を抱えているが、質は違えど実は根本は極めて似通った問題で苦悩し続けている
・それらの問題を解決する手段のひとつとして地域力が求められている
・日本の後を追うように今後急速に高齢化の道を辿るアジアの他の国々は、一足早く正念場を迎えている日本がどう乗り切るかを注視しているのでうまく乗り切れば新しい社会モデルをアジアに示すことになる
・自然から搾取するのではなく自然と共に生きてきた日本人の強みと島国という日本の地理的強みなど地域力を高めやすい要素が揃っている
と話されました。
その後、川井氏が早川先生を紹介され、早川先生から「三河中山間の地域力を考える」~中山間地域における当院の取り組み~というタイトルで、スライドを用いながらの趣旨説明が始まり、病院と研究会の両方について様々な取り組みの詳細を語られています。
基調講演は「日本の里山に生きること」というタイトルにて澁澤寿一氏が
・日本は(2011年の)3月11日を境に変わった、高度成長の末に震災を経て全部を都会に集中させる社会から分散型社会に舵が切ろうとする人々が現れ始めた
・しかし実はそもそも日本は昔から地域の独立性で生きてきた国だった
・人任せの社会からもう一度自分たちでものを考える社会にすべきだと思う
・地球一個は足りなくなっている、つまりこのままでは70億人が地球一個で生きられなくなる時が訪れてしまう
という問題提起をされたのち、ご自身が秋田の山奥の集落をこの20数年間訪ね続けているというエピソードを紹介されます。その昔、秋田では過去に大規模な飢饉が起きて大勢の人々が命を落としているが、その集落では古文書が残っている過去300年間において一人の餓死者も出していないというのが通い出したきっかけだそうです。ここには書きませんが、その秘密はとても興味深いものでした。
他にも、山形の置賜地方の草木塔や馬頭観音、庚申塚、お不動さんの写真を紹介し、人々が自然といかに共生しようとしてきたかについて語られたり、沖縄のオジイ、オバアが生きる上で大切にしているポリシーのようなものの紹介など、その場でぜひ聴きたかったと思えるエピソードが続きます。
・生活はつくるものだということがもう一度見直される
・そして中山間地域での生き方がもう一度見直される時代がくると思っている
澁澤さんは聴衆に向かってそう語りかけています。
コーディネーターの農協共済総合研究所 川井氏に促され、足助病院長の早川富博先生と澁澤寿一氏が再び壇上に上がり、フロアーからの質疑応答の時間となりました。
地元の高校生からは
・少子高齢化となってきているのを自身も感じている
・もっと若い人たちが活発に暮すことができれば子供が増えていくのかなと思う
というような発言があり、それに対して早川先生からは
・ここ数十年に繰り広げられたような消費社会のままでいくのか、50年前の暮しに戻るのか、50年前と現代の中間みたいなところを目指すのか、若い世代の方が今後どのような生活を目指すのかがポイントになるのでは
とのコメントが。
澁澤氏は
・足助は底を打って上がり始めているのかもしれないと思う
・空家バンクに申込者が殺到したりしている状況があり、若夫婦が都会から何組かやってきている
・年にひと組ぐらいずつ入ってくるだけで数が確実に維持できるし、あるいは上がってくる
・都会からやってくる若者を各集落が温かく抱え込んでいただければ多分順調に足助は伸びてゆくと感じる
・年収700万、1000万を目指しましょうという時代ではないと思う。
と語られ、消費に重きが置かれたこれまでの生活に最早価値観を見いださず、心身ともに豊かに暮らすためにむしろ生活のサイズダウンすることを望む若者が増えているとおっしゃっています。
そして
・豊田の中山間地域は人が今まで出て行った比率がものすごく大きいからその人たちが帰ってくる余力は他のところに比べたら全然違う
・このあたりの若い人たちは旧豊田市内やせいぜい名古屋など、週に一回実家に帰ろうと思えば帰ることが出来る近距離に出ている人が多いため地域とのつながりが確実に残っている。
・都市と中山間地を組み合わせた生活、そういう生き方をチョイスしたいと若い人たちが思えばものすごくチョイスができる魅力的な地域だと思う
と続けられます。
コーディネーターの川井氏が澁澤氏の発言に「目からうろこでした。」と言われ、フロアーにいる聴衆が思い浮かべるイメージがさらに膨らむように
・ある程度の産業が整った町と、農林業を中心とした山間部での第一次産業とのコラボレーションがとりやすい地域なのかもしれない
と補足のコメントをされました。
そして、「ほかにどうですか。何か今のお話を聞いて。」と会場に呼びかけます。
すると、79歳の方がマイクを握って次のようなことを語り始めました。
・昔の生活はつらかった。親父と一緒に山に行き炭を焚き、雨が降っても田植えをする、それも手で。一日中這いつくばっていて腰が痛くてしょうがない。同時にお金もない。百姓と、山仕事と、貧乏が一番嫌いだった。
・その後、石油を利用するようになり、新幹線や車が走る時代になり、百姓をやるにも、移動をするにも文明の恩恵を受けてきたが、それはそれで昔のつらい暮らしぶりのことを思えば意義があると思える。
・決して間違いではなかったと思うが、地球環境の良くない変化だとか、身近なところでは山が荒れて、耕地も荒れてという様子になってきたのを見て、自然に寄りそう暮らしを望む人々が現れるのは、人間が長く生きる間のサイクルとして理解できる。
・早川先生は「会をつくってこれからみんなでやっていく、会員には息子や孫を入れていく」ということをおっしゃっていたが、「田舎に帰ってこいよ」という話があってもなかなか思うようにはいかない現実があるし、どういう風に手をつけて良いのかと思い悩んでいるこの足助が渋澤先生がおっしゃったように本当に良い方向に今後進んでいけるのか、ジリ貧ではないのか、と不安に思う。
・しかし弱気にならずに、力強く生きていかねばならない、とも思っている。
と正直な気持ちを語られました。
澁澤氏は
・まさにおっしゃったサイクルで、もう一回どこまで戻れるかを探していくことになり、それは地域ごとの個性になってくると思う
・お婆ちゃんたちに、どこまでだったら戻れるかと聞いたことがある。つらい暮らしを変えてくれた農業機械の話で例えて考えてもらったら、我々は便利さをとっくに通過してしまったことがわかった
・これからは確実に、便利になっていくのではなく、ある不便さを伴う形に世の中全体が、都市だ地方だということに関わらずなっていくが、それをどう喜びに変えられるかというのは、その地域の知恵だと思う
・あの時代に戻れとは思っていないが、行き過ぎてしまったことだけははっきりしている
・一体どこまで戻れるかということを皆さんと考えていくことが大事であり、その中のひとつが医療の問題なのかなと感じる
早川院長は
・ジリ貧ということで言えば、病院を立て直すときに人口推移のシミュレーションをしたところ、いまのままでいったとしても20年後までは大丈夫という試算 (病院経営が可能という試算) がなされた、しかし地域の人口は少しずつ減っていく
・外に出たご子息も定年退職されたら帰ってくればいい、帰ってきたところに楽しい地域を作っておく、じじばばが住むには医療と介護のセーフティネットが必要、セーフティネットにお金をかけすぎてはいけないのでお金をかけずにどういうセーフティネットをつくるのかというのがぼくらが考えること
・お金が入らない病院は消滅してしまうかもしれないが、そうではないという政策・方法をかんがえた場合は予防医学でいくことになる
・これからは、いかに生きるかということはいかに死ぬかということとイコールになる
・死に方にはいろいろあって良いはずで、家で、病院で、施設で、と最後の最後のところでは選択肢がいろいろあるという多様性を社会がある程度担保するのが理想
・健康的に生きる、あまり病まないように生きるための予防的な医療をしていきたい
・この地域で60代以上の方が楽しみをもって元気でいきいきと生きていることが大事、僕らはみなさんが安心していきいきとされるためのセーフティネットで下支えをするつもりである、そしてそれはできるのではないかと思っている
と、それぞれ心強いコメントを返されました。
(ここからはさらに数名の方々が登壇されとても有意義なシンポジウムが行われたのですが、近々2012年のシンポジウムのことも記事としてアップしなければなりませんので、おととしの開催記録の紹介はこのあたりでいったんおわりたいと思います。
また別途ご紹介する機会もきっと訪れようかと思いますし、もしも記録をすべて読んでみたいと思われた方は研究会または山里センチメンツに直接コンタクトしていただいても構いません。コピーを貸出させていただきます。)
また別途ご紹介する機会もきっと訪れようかと思いますし、もしも記録をすべて読んでみたいと思われた方は研究会または山里センチメンツに直接コンタクトしていただいても構いません。コピーを貸出させていただきます。)
2013年01月01日
安心して暮らし続けるためのネットワーク構築に向けて

安心して暮らし続けるための保健・医療・福祉(介護)ネットワーク構築に向けて ‐中山間地における効率性の追求‐
1.現状認識
農山村地域における医療・福祉(介護)の課題は過疎に起因しています.
すなわち,市場が成立しない農山村では,交通機関の撤退を含む公共サービスの低下(不均衡),民間業者が参入しないための医療機関,介護保険サービス不足が問題であります.このような安全性の欠落や不便さが人口流出に拍車をかけています.
2.目標設定
その解決に,都市部と農山村部の共生を掲げた住民運動が必要であることは言を俟ちませんが,地域との連携を基本的とした,少ないサービスの効率的運用を目指すことが重要であります.中山間地域の健全な維持なくして,下流(都市部)に住む人びとの安全はなく,その維持には,ある程度の人びとが住む必要があり,そのために教育・保健・医療・福祉・介護サービスが必須であります.
3.効率性追求
効率性を,より少ない対価で高い成果(満足)を得ることと仮定すれば,市場が成立する都会(人口密度が高い地域)では,競争原理で効率性が高まる可能性?がありますが,市場がない中山間地では,各分野の資源・サービスが絶対的に不足しているので,助け合いや協働なくして効率性を高めることはできません.住民に対するサービスの代表である行政のそれは,決して縦割りにならないように配慮することが重要であります.健康を守ることを目的とする保健・医療・介護サービス分野でも,連携・合体をもってその効率性を追求することが肝要であり,そのためにはまず保健・医療・福祉・介護の情報の共有化が欠かせません.
4.保健・医療・介護情報の共有
本来,個人の保健・医療・福祉・介護情報はその個人自身で管理すべきでありますが,これまでお上が絶対的権威を示してきた歴史的背景,任せていれば安心という日本人には,まだそのような慣習が形成されていません.
75歳の一人の住民を想定したとき,その人の健診データ(保健情報)は行政の保健福祉部門に保存,高血圧症,高脂血症,糖尿病などの疾病によるデータは医療機関(慢性疾患は診療所,急性疾患は病院など)に蓄積されています.介護保険認定を受ける状態になれば,その調査データは介護保険課に貯められ,続いて提供される介護サービス時の状況をみれば,各サービス業者に個々に作成された福祉カルテに記録され,主治医の意見書は診療所のカルテに保存されています(図1).
1.現状認識
農山村地域における医療・福祉(介護)の課題は過疎に起因しています.
すなわち,市場が成立しない農山村では,交通機関の撤退を含む公共サービスの低下(不均衡),民間業者が参入しないための医療機関,介護保険サービス不足が問題であります.このような安全性の欠落や不便さが人口流出に拍車をかけています.
2.目標設定
その解決に,都市部と農山村部の共生を掲げた住民運動が必要であることは言を俟ちませんが,地域との連携を基本的とした,少ないサービスの効率的運用を目指すことが重要であります.中山間地域の健全な維持なくして,下流(都市部)に住む人びとの安全はなく,その維持には,ある程度の人びとが住む必要があり,そのために教育・保健・医療・福祉・介護サービスが必須であります.
3.効率性追求
効率性を,より少ない対価で高い成果(満足)を得ることと仮定すれば,市場が成立する都会(人口密度が高い地域)では,競争原理で効率性が高まる可能性?がありますが,市場がない中山間地では,各分野の資源・サービスが絶対的に不足しているので,助け合いや協働なくして効率性を高めることはできません.住民に対するサービスの代表である行政のそれは,決して縦割りにならないように配慮することが重要であります.健康を守ることを目的とする保健・医療・介護サービス分野でも,連携・合体をもってその効率性を追求することが肝要であり,そのためにはまず保健・医療・福祉・介護の情報の共有化が欠かせません.
4.保健・医療・介護情報の共有
本来,個人の保健・医療・福祉・介護情報はその個人自身で管理すべきでありますが,これまでお上が絶対的権威を示してきた歴史的背景,任せていれば安心という日本人には,まだそのような慣習が形成されていません.
75歳の一人の住民を想定したとき,その人の健診データ(保健情報)は行政の保健福祉部門に保存,高血圧症,高脂血症,糖尿病などの疾病によるデータは医療機関(慢性疾患は診療所,急性疾患は病院など)に蓄積されています.介護保険認定を受ける状態になれば,その調査データは介護保険課に貯められ,続いて提供される介護サービス時の状況をみれば,各サービス業者に個々に作成された福祉カルテに記録され,主治医の意見書は診療所のカルテに保存されています(図1).

このような個人のデータが分散された状態でもって,「医療と介護の連携が重要である」と行政指導は行われ,連携のために時間とお金を費やしています. 分断されている保健・医療・福祉・介護情報を一体化すれば,日常診療に大いに役立ち,検査の無駄を省くことができ,結果として医療費の削減につながることが想定されます(図2).

また,保健活動からみれば,保健師による保健指導と医療現場での指導との無駄のない連携が図られますし,医師からみれば,連携のために要求される書類を書く負担も大いに軽減されます.人の一生の生活の質を支え維持するのは保健・医療・福祉・介護サービスであり,その一体化(同じ意思を持った.同じベクトル)が少ないサービスを効率よく運用する鍵であります(図3).

5.もう少し先へ
地域で病気の人が増えれば医療機関の経営が安定し,保健活動によって早期発見,早期治療が確立されれば医療機関の経営が圧迫されるという現在の医療制度では,住民の健康を守るという根本的な理想に近づけません.いままでの医療から予防医療である検診の充実―保健事業へのシフトが結果的に地域住民の幸せにつながると思います.
保健・医療・福祉・介護情報が共有化され,誰でもどこでも必要な情報を得ることができる状況下,適切なサービスを提供できる体制づくりを,行政,民間を含めて構築することが健康な地域づくりの基本でありましょう.
6.まとめ
中山間地域の健全な維持なくして,下流(都市部)に住む人びとの安全はありません.その維持には,ある程度の人びとが住む必要があり,そのためには医療・福祉(介護)サービスが必須であります.競争・市場が成立しない中山間部では,縦割り組織による分断的サービスではなく,情報の共有化とそれに基づく効率的な連携(合体)した住民へのサービス提供が重要あります.そのためには一律の法律に基づく均一な政策でなく,柔軟で多様な公的援助が必要であり,住民が作り上げる仕組みを行政が追認するという方策を採らない限り農山村地域の生存権を支える医療・福祉サービスの維持は不可能であります.
いわゆる田舎の生活基盤を支えてきた郵便局が分社化・解体されてしまった現在,地域を総体として捉える考えを基礎にもった公民・公協連合の模索が必須と考えます.
文責:"三河中山間地域で安心して暮らし続けるためのネットワーク研究会"
地域で病気の人が増えれば医療機関の経営が安定し,保健活動によって早期発見,早期治療が確立されれば医療機関の経営が圧迫されるという現在の医療制度では,住民の健康を守るという根本的な理想に近づけません.いままでの医療から予防医療である検診の充実―保健事業へのシフトが結果的に地域住民の幸せにつながると思います.
保健・医療・福祉・介護情報が共有化され,誰でもどこでも必要な情報を得ることができる状況下,適切なサービスを提供できる体制づくりを,行政,民間を含めて構築することが健康な地域づくりの基本でありましょう.
6.まとめ
中山間地域の健全な維持なくして,下流(都市部)に住む人びとの安全はありません.その維持には,ある程度の人びとが住む必要があり,そのためには医療・福祉(介護)サービスが必須であります.競争・市場が成立しない中山間部では,縦割り組織による分断的サービスではなく,情報の共有化とそれに基づく効率的な連携(合体)した住民へのサービス提供が重要あります.そのためには一律の法律に基づく均一な政策でなく,柔軟で多様な公的援助が必要であり,住民が作り上げる仕組みを行政が追認するという方策を採らない限り農山村地域の生存権を支える医療・福祉サービスの維持は不可能であります.
いわゆる田舎の生活基盤を支えてきた郵便局が分社化・解体されてしまった現在,地域を総体として捉える考えを基礎にもった公民・公協連合の模索が必須と考えます.
文責:"三河中山間地域で安心して暮らし続けるためのネットワーク研究会"
2013年01月01日
ごあいさつ
January
2013

新年あけましておめでとうございます。
"三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会"
というとても長いなまえの研究会の、サポーターブログをこのたび立ち上げました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
タグ :三河中山間
2013年01月01日
目的・テーマ・事業等についてのご紹介

三河中山間地域で安心して暮らし続けるためのネットワーク研究会の事務局は、愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院内に設置されています。
以下は、事務局が発信している研究会の目的、テーマ、事業、および当面の活動についての紹介文章です。
以下は、事務局が発信している研究会の目的、テーマ、事業、および当面の活動についての紹介文章です。
研究会の目的
本会は、三河中山間地域で安心して暮らし続けるために必要な、医療・保健・福祉(介護)サービスを安定して確保することを目的とする。
三河中山間地域は、診療所を始めとする医療・保健・福祉の資源が少ない。
さらに昨今の医師不足・看護師不足は当地域へも波及して、足助病院においてもそうした問題が表面化してきている。
これらのサービスは地域住民に包括的に提供できてはじめて実効ある活動となるが、以下のように医療費削減を目的とした政府による制度変更はこれを妨げる方向に進んでいるとしか思われない状況である。
即ち、1980年代から進められた介護では介護保険制度を制定、保健分野では健康に対する自己責任の明確化などの打ち出し、1983年から老人保健法で実施してきた健康診断や保健指導を医療保険に移した事などである。
こうした制度の変更は、制度ごと・財源ごとの縦割り組織による事業活動を行なわざるを得ない現状をもたらしており、サービス提供事業者は各々をバラバラに事業活動をせざるを得なくなっている。
また、自由開業医制下における市場原理主義・規制改革・民間開放に傾いた施策は、ただでさえ不足している三河中山間地域のサービス資源を枯渇化させている。
一方では、健診時の検査と病院での検査が二重に実施されても抑止する手段が無いなど、結果的には費用の無駄を発生させている事例も多くある。
このような状況における医師不足・看護師不足問題は、2次医療圏内の医療提供体制崩壊の危惧に結びついており、とくに距離的不利益と医療資源を始めとする供給体制不足に起因する社会生活面での不安が大きい三河中山間地域では、地域に暮らすもの自らが「健康面での安全・安心の確保」に立ち上がる必要があるのではないかと考える。
その方策の一つとして、「病気にならない、介護を受けずにすむ健康づくり」を中心とした健康に対する価値観の醸成と個人を支援する仕組みを作る事が挙げられる。
今一つは、これまでは実現できなかった医療・保健・福祉サービスの連携の形態を探り、少ない資源を有効に連携活用したサービスの一元的提供を目指し、三河中山間地の健康に関する安全・安心を確保するネットワーク体系を構築する。
「三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会」では、人と人とのヒューマンネットワークづくりを進めるなかで、個々の健康意識の調査および地域に必要なサービス(機能)などの調査をしたうえで、抽出された課題や共有できる目標に向かって活動していきたいと考えている。
テーマ
住民の健康意識の醸成と健康に関する安心感の確保
サービス提供者側のネットワークの構築
住民とサービス提供者側ネットワーク構築
課題解決のためのツール開発
研究会の事業
・地域の啓発に必要な集会、講演会の開催
・住民の健康づくりを促す仕組みづくり、医療・保健・福祉サービスの連携によるサービスの一元(ネットワークサービス)提供の研究
・森林の割合が90%、高齢化率40%、進む過疎化という三河中山間地域の特性を克服するためのICT利活用の研究
・ネットワークサービスの事業化の研究
当面の活動について
1.住民の健康意識の醸成:研究会の広報活動、研究会への参加呼びかけ。講演会や健康講座の開催。
2.保健・医療・福祉(介護)関係者への研究会の広報活動、研究会への参加呼びかけ
3.住民の実態及び意識調査の実施と現状の分析・課題の把握
4.サービス提供者の実態と意識調査の実施と現状の分析・課題の把握
5.課題解決のための分科会を設置して解決にあたる。
※.現在進めているWeb型電子カルテを活用した地域での医療情報共有活用の取組み等ICT利活用の研究は分科会活動として継続していく。
本会は、三河中山間地域で安心して暮らし続けるために必要な、医療・保健・福祉(介護)サービスを安定して確保することを目的とする。
三河中山間地域は、診療所を始めとする医療・保健・福祉の資源が少ない。
さらに昨今の医師不足・看護師不足は当地域へも波及して、足助病院においてもそうした問題が表面化してきている。
これらのサービスは地域住民に包括的に提供できてはじめて実効ある活動となるが、以下のように医療費削減を目的とした政府による制度変更はこれを妨げる方向に進んでいるとしか思われない状況である。
即ち、1980年代から進められた介護では介護保険制度を制定、保健分野では健康に対する自己責任の明確化などの打ち出し、1983年から老人保健法で実施してきた健康診断や保健指導を医療保険に移した事などである。
こうした制度の変更は、制度ごと・財源ごとの縦割り組織による事業活動を行なわざるを得ない現状をもたらしており、サービス提供事業者は各々をバラバラに事業活動をせざるを得なくなっている。
また、自由開業医制下における市場原理主義・規制改革・民間開放に傾いた施策は、ただでさえ不足している三河中山間地域のサービス資源を枯渇化させている。
一方では、健診時の検査と病院での検査が二重に実施されても抑止する手段が無いなど、結果的には費用の無駄を発生させている事例も多くある。
このような状況における医師不足・看護師不足問題は、2次医療圏内の医療提供体制崩壊の危惧に結びついており、とくに距離的不利益と医療資源を始めとする供給体制不足に起因する社会生活面での不安が大きい三河中山間地域では、地域に暮らすもの自らが「健康面での安全・安心の確保」に立ち上がる必要があるのではないかと考える。
その方策の一つとして、「病気にならない、介護を受けずにすむ健康づくり」を中心とした健康に対する価値観の醸成と個人を支援する仕組みを作る事が挙げられる。
今一つは、これまでは実現できなかった医療・保健・福祉サービスの連携の形態を探り、少ない資源を有効に連携活用したサービスの一元的提供を目指し、三河中山間地の健康に関する安全・安心を確保するネットワーク体系を構築する。
「三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会」では、人と人とのヒューマンネットワークづくりを進めるなかで、個々の健康意識の調査および地域に必要なサービス(機能)などの調査をしたうえで、抽出された課題や共有できる目標に向かって活動していきたいと考えている。
テーマ
住民の健康意識の醸成と健康に関する安心感の確保
サービス提供者側のネットワークの構築
住民とサービス提供者側ネットワーク構築
課題解決のためのツール開発
研究会の事業
・地域の啓発に必要な集会、講演会の開催
・住民の健康づくりを促す仕組みづくり、医療・保健・福祉サービスの連携によるサービスの一元(ネットワークサービス)提供の研究
・森林の割合が90%、高齢化率40%、進む過疎化という三河中山間地域の特性を克服するためのICT利活用の研究
・ネットワークサービスの事業化の研究
当面の活動について
1.住民の健康意識の醸成:研究会の広報活動、研究会への参加呼びかけ。講演会や健康講座の開催。
2.保健・医療・福祉(介護)関係者への研究会の広報活動、研究会への参加呼びかけ
3.住民の実態及び意識調査の実施と現状の分析・課題の把握
4.サービス提供者の実態と意識調査の実施と現状の分析・課題の把握
5.課題解決のための分科会を設置して解決にあたる。
※.現在進めているWeb型電子カルテを活用した地域での医療情報共有活用の取組み等ICT利活用の研究は分科会活動として継続していく。
タグ :三河中山間
2013年01月01日
発足経緯のご紹介

三河中山間地域で安心して暮らし続けるためのネットワーク研究会の事務局は、愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院内に設置されています。
以下は、2010年に事務局が発信した研究会の発足経緯を紹介した文章です。
以下は、2010年に事務局が発信した研究会の発足経緯を紹介した文章です。
研究会発足に至る経緯
当院では、この地域に生活する地域住民の安全・安心・満足な生活を確保するためには、保健・医療・福祉(介護)サービスの存続と確保、その連携は必須の要件であるとの考え方から、現在Web型電子カルテを活用した地域での医療情報共有活用の取組みを厚生労働省の「地域診療情報連携推進事業補助金」の採択を受け進めています。
この取組みは三河中山間地域に在る診療所の医療情報と当院の医療情報を地域共有カルテの構築により相互活用して地域医療の向上と機能連携に貢献しようとするものです。
この取組みの中で地域の診療所の先生方と意見調整や要望など自由に討論できる場としての「意見交換会」を既に5回開催してきました。(※2010年当時の回数です)
この意見交換会では、この地域における医療・保健・福祉の存続が地域住民の安心した生活には不可欠であるとの考え方に立って討論が為されており、今回のWeb型電子カルテによる医療情報の共有に留まるのではなく広い視野に立って地域の方向性を考える必要があるとの考え方で意見が一致していました。
このことから「三河中山間地域で安心して暮らしつづけるための健康ネットワーク研究会」の設立について先生方の賛同を得、発足の運びとなりました。
また、この研究会には診療所の医師のみでなくこの地域の診療所スタッフ・保健福祉関連施設職員・自治体関係者・農協関係者・地域住民など幅広い参加を求めることが確認されました。
以上のような経緯から「自分たちの手で地域の健康に関する安全・安心を確保する」を目標に掲げた研究会として発足することにしました。
この取組みは三河中山間地域に在る診療所の医療情報と当院の医療情報を地域共有カルテの構築により相互活用して地域医療の向上と機能連携に貢献しようとするものです。
この取組みの中で地域の診療所の先生方と意見調整や要望など自由に討論できる場としての「意見交換会」を既に5回開催してきました。(※2010年当時の回数です)
この意見交換会では、この地域における医療・保健・福祉の存続が地域住民の安心した生活には不可欠であるとの考え方に立って討論が為されており、今回のWeb型電子カルテによる医療情報の共有に留まるのではなく広い視野に立って地域の方向性を考える必要があるとの考え方で意見が一致していました。
このことから「三河中山間地域で安心して暮らしつづけるための健康ネットワーク研究会」の設立について先生方の賛同を得、発足の運びとなりました。
また、この研究会には診療所の医師のみでなくこの地域の診療所スタッフ・保健福祉関連施設職員・自治体関係者・農協関係者・地域住民など幅広い参加を求めることが確認されました。
以上のような経緯から「自分たちの手で地域の健康に関する安全・安心を確保する」を目標に掲げた研究会として発足することにしました。
タグ :三河中山間
2013年01月01日
香嵐渓シンポジウム2012
素晴らしい秋晴れとなった2012年10月20日の土曜日。
豊田市足助町の飯盛座にて香嵐渓シンポジウムが開催されました。
近々その様子をご紹介します。
少々お待ち下さい。
豊田市足助町の飯盛座にて香嵐渓シンポジウムが開催されました。
近々その様子をご紹介します。
少々お待ち下さい。